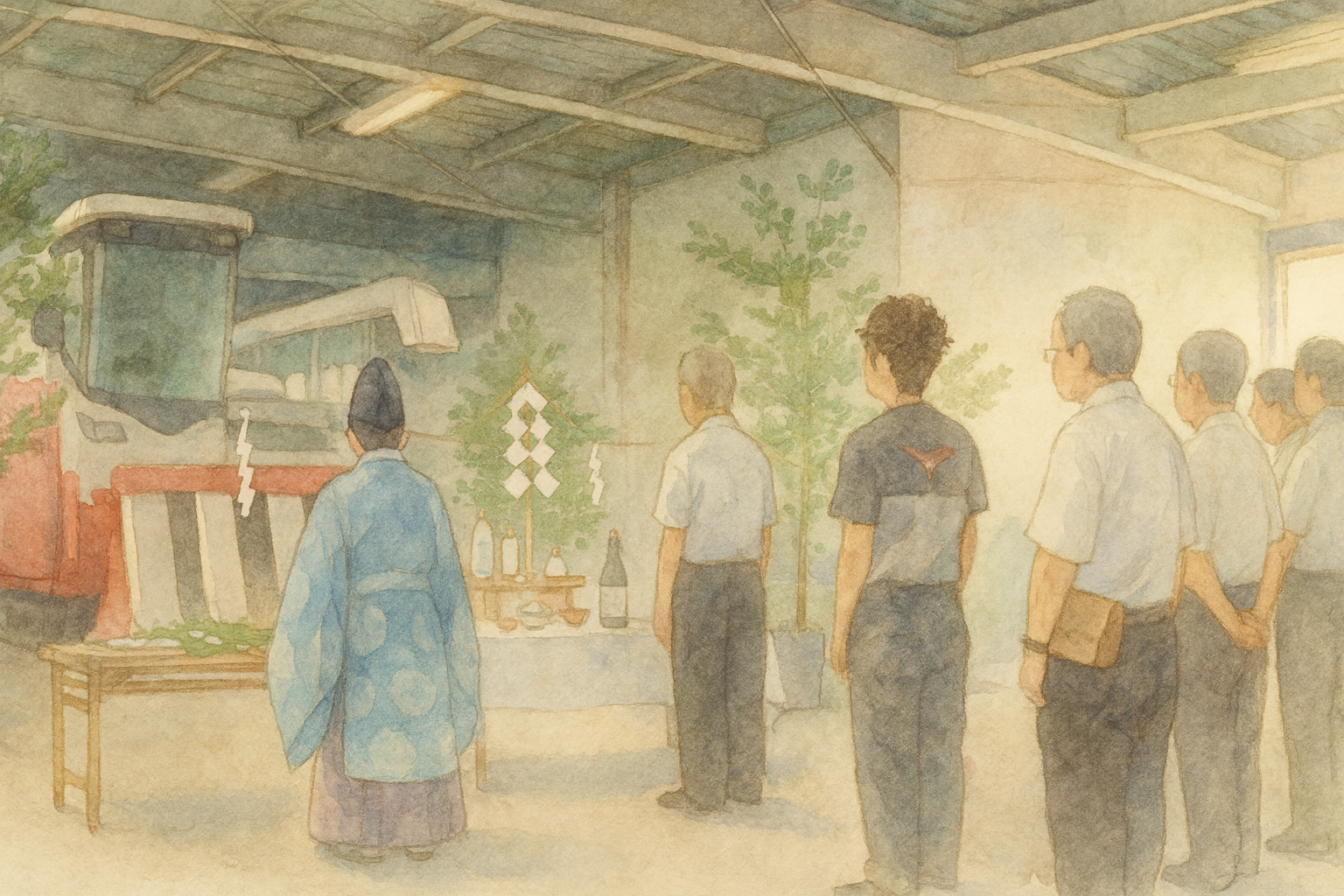南箕輪村議会2025年9月定例会の一般質問で原源次議員への答弁内容です。
Q1 担い手、後継者不足と言われて久しいが、村として今後取り組む方法はあるか。
担い手・後継者不足への今後の取組についてお答えいたします。
まず現状でございますが、全国的な動向と同様に、本村におきましても、産業課窓口へ「農地の維持管理が難しい」「借り受け手を紹介してほしい」といったご相談が増加しております。
一方で、会社員等からの転身や家業の承継による就農を希望される方からのご相談も、ここ数年は年間おおむね5件ほど頂戴しております。認定新規就農者は、令和5年度が1夫婦、令和6年度が3夫婦、令和7年度は3夫婦に加えて単身1名であり、着実に芽が育ちつつある状況でございます。
これまでの取組として、独自の補助制度は設けておりませんが、農業委員会と連携した個別相談の実施、JAのインターン研修、県の里親研修、国の新規就農者向け各種支援制度のご案内を行っております。
あわせて、就農希望の内容を整理する「新規就農相談カード」を作成し、本人の同意のもとでJAや長野県農業農村支援センター等と情報共有を図り、希望に沿った就農につながるよう体制を整えております。
引き続き、関係機関と緊密に連携し、相談から就農、定着までの支援に努めてまいります。
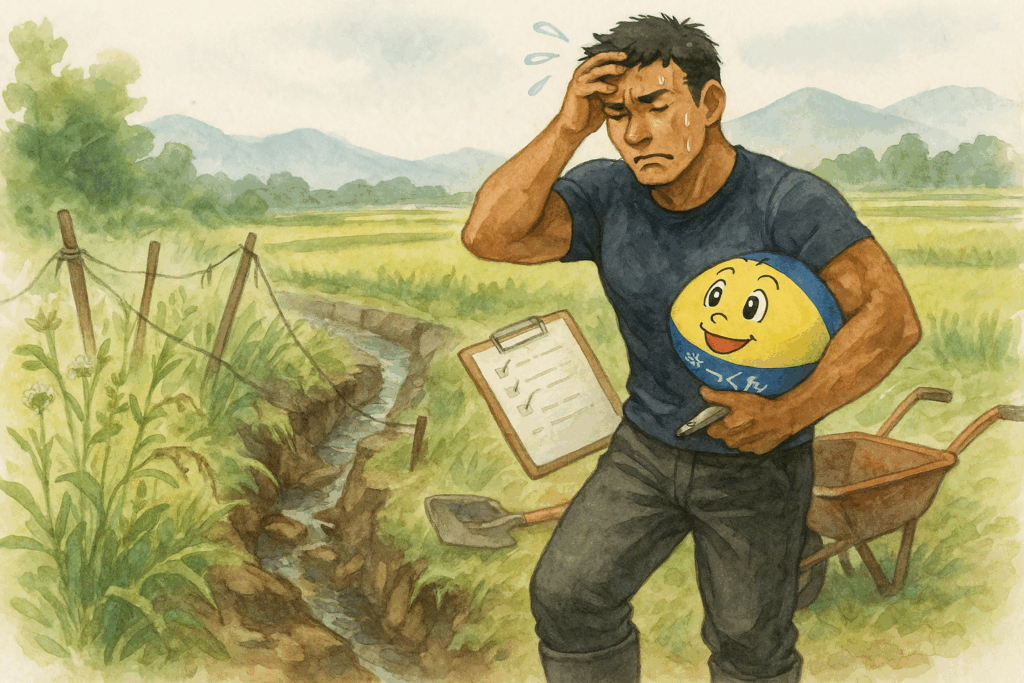
Q2 昨年度各地区で、10年後の地域農業の在り方等が話されたがその結果は、内容は。
昨年度実施いたしました、各地区における「10年後の地域農業の在り方」に関する懇談の結果について、お答えいたします。
令和6年6月の沢尻地区を皮切りに、9月末の大芝地区まで、9地区に分けて懇談会を開催し、各地区公民館および村役場にて、延べ228名の農業者・関係者の皆さまにご出席いただきました。
これは、令和6年度内に策定が必要であった「地域計画」に、①地域の農業における問題点・課題、②課題解消のためのアイデアを地域主体の話し合いで取りまとめ、反映するために実施したものであります。
各地区での議論を通じて、共通する主な課題としては、①高齢化、②人手不足、③草刈り等維持管理の負担、④所得の伸び悩みが挙げられました。
要因として、収入の不安定さ・低所得化、肉体労働による負担の大きさ、分散圃場による非効率などが指摘されております。
一方、解決に向けた具体的なアイデアとして、草刈り省力化に資する技術・機械の導入、村による農業機械貸出制度の検討、農道・水路・圃場の小規模改良や団地化の推進、スマート農業の導入・拡大等が示されました。
これらの課題と方策は「地域計画」の記載事項として整理済みであり、地域の皆さまの思いを受け止め、村としても関係機関と協議しながら実行可能なものから着実に進めてまいります。
さて、本地域計画は昨年度の話し合いで完結するものではございません。とりわけ「10年後の耕作者をどのように確保・明確化するか」は引き続いた大きな論点であり、全国的にも“10年後の耕作者未定農地が5割超”との公表があるなど、喫緊の課題であることが共通認識であります。本村においても昨年度は「10年後は見通しが立たない」とのご意見が多く寄せられました。
そこで、本年も農業委員会と連携し、継続して地域計画の話し合いを進めてまいります。
その際、①地区ごとの将来耕作者の見える化、②出し手・受け手や作業受委託・機械共同利用のマッチング、③草刈り・獣害・用排水等の負担軽減策の標準化、④進捗指標の定点把握といった観点を取り入れ、地域で「10年後の農地をどう守り、誰が担うか」を具体的に考え、合意形成を図る機運を高めてまいります。
Q3 農業労働省力化のため、圃場の集約・機械化等が叫ばれているが初期費用が多くかかる為、補助事業導入など有利な方法はないか。
圃場整備と機械導入についての支援についてお答えいたします。
まず、現状でありますが、個人が行う圃場整備に対する村独自の補助制度は設けておりません。
もっとも、県の農業開発公社が関与する農地中間管理事業を活用した場合、要件を満たせば圃場整備に対する補助を受けることができます。
久保地区では、同事業の貸付要件を踏まえた圃場整備の検討機運が高まっており、村としても必要に応じて県等から最新情報を収集し、地域への的確な情報提供と手続き面の支援に努めてまいりたいと考えております。
次に、圃場の集約・効率化についてであります。
西天の水田地域では一筆当たり約10アールの区画が多く、機械の大型化が進む中で作業効率が上がりにくい実情がございます。
区画拡大や形状の整理といった「圃場整備」を進めることが、生産性向上と労力軽減に直結いたします。
そのため、地域の合意形成を大切にしながら、農地中間管理事業の活用も視野に、段階的な取り組みを後押ししてまいります。
次に、機械・施設導入支援について申し上げます。
従来、国・県の補助事業は大規模農家や農業生産法人が主な対象であり、個人経営の農業者にとっては資金調達の負担が大きい課題がございました。
そこで令和7年度から、村単独費による「担い手農業者農業機械等導入補助金事業」を創設し、地域の模範的農業者である認定農業者を対象に、15万円以上の導入経費に対し3割、上限30万円を補助することといたしました。
https://www1.g-reiki.net/vill.minamiminowa/reiki_honbun/e747RG00000888.html
申請期間であった7月末までに、11事業体から総額2,634千円分の申請があり、8月上旬に交付決定を行っております。
申請のあった主な機器・資材は、草刈り用モア、根菜掘取り機、ビニールハウス屋根資材、肥料散布機、除草機などで、現場の省力化・効率化に直結する内容でございます。
執行状況は予算ベースで約9割と、ニーズを的確に捉えた制度設計であったと受け止めております。
最後に今後の方向性であります。
まずは本年度創設した機械等導入補助を着実に運用し、費用対効果、導入後の作業時間短縮や維持管理負担軽減の実績を検証いたします。
その結果を踏まえ、来年度以降、対象者や上限額等の見直しを含め制度の改善を検討してまいります。
あわせて、圃場整備につきましては、久保地区をはじめ機運の高い地域での合意形成支援、制度情報の提供、関係機関との調整を進め、農道・用排水・区画整理等の小規模改良も含め、実行可能な手立てから段階的に取り組んでまいります。
引き続き、農業委員会、JA、県関係機関と緊密に連携し、圃場の集約・整備と機械導入の両輪で省力化・収益性向上を後押しすることで、担い手の定着と地域農業の持続可能性の確保に努めてまいります。
Q4 困ったときのまっくんファームだが、高齢化・作業者不足等対応が難しくなっている。持続可能な運営の支援方法は。
農事組合法人まっくんファームは、平成23年の法人化以来、地域農業の受け皿として期待を一身に担い、年々その役割が大きくなっております。
現在、組合員は約550人、役員5名(代表理事1名を含む)、事務局1名の体制で、農地の借受けや作業受託を中心に、風の村米だよりをはじめとした水稲・麦・大豆・そばの作付け、播種・防除・収穫等の一連作業を通年で担っていただいております。
繁忙期には限られた人員で作業をやり切るご苦労も承知しており、本村の水田地帯を支える不可欠な基幹担い手であると認識しております。
村としてはこれまで、法人運営費および機械購入費に対する補助を実施してまいりました。
今後は、まっくんファームの皆さまとの意見交換を重ねながら、支援方法の具体化を進めてまいります。
とりわけ人的支援を軸に、実効性のある支援を立案できるよう取り組んでまいります。