南箕輪村に移住して感じたことの一つに、冷涼地であるため田植えや収穫の開始時期が比較的遅いという点がありました。
冷涼地である南箕輪村の農作物の生育や収穫時期について、調べていきたいと思います。シリーズ1は稲作と麦です。
令和6年度の状況も参考に、どのような時期にどのような作業が行われてきたのかを調べてみました。
1 稲作
育苗期(4月)
上伊那地域の播種のピークは4月14日頃となっています。
- 令和6年度は、高温傾向により徒長(とちょう)気味で、一部でヤケやもみ枯れ細菌病が発生していましたが、概ね順調でありました。
本田期前半(田植え~6月中旬)
上伊那地域の田植えは、5月連休中から本格化していき、ピークは5月19日頃となっています。
- 令和6年度は、直播栽培は5月4日から10日にかけて播種が行われ、順調に出芽がそろいました。
- 初期生育は気温と日照に恵まれ、6月14日時点で草丈は平年比109%、茎数は144%とともに平年を大きく上回りました。
- 田植えから40日後の6月24日には草丈109%、茎数117%と依然として高い水準を維持し、50日後の7月4日には草丈105%、茎数105%となり、最高分げつ期を経過しました。
- 同日、幼穂形成期に達し、これは平年より3日早く、前年より4日早い時期でした。
- 田植えから60日後の7月14日には、草丈103%、茎数103%となり、生育は平年並みとなりました。
- 出穂期は「コシヒカリ」で7月27日となり、平年より4日、前年より2日早まりました。
- 病害虫の発生状況としては、葉いもちは6月30日から7月3日、7月14日から16日にかけて感染に好適な条件となりましたが、穂いもちは8月の高温により発生が少ない状況でした。
- 一方、斑点米カメムシ類ではホソハリカメムシの多発が目立ち、斑点米の発生が全般的に多くなりました。
成熟・収穫期(9月)
上伊那地域の稲刈りは、9月4日からカントリーが稼働し、本格収穫が開始され、ピークは9月15日頃となり、10月5日頃には終了となります。
- 令和6年度は、成熟期は「コシヒカリ」で9月7日となり、平年より9日、前年より3日早まりました。
- 9月は好天の日が多く、収穫作業は順調に進みました。
2 麦
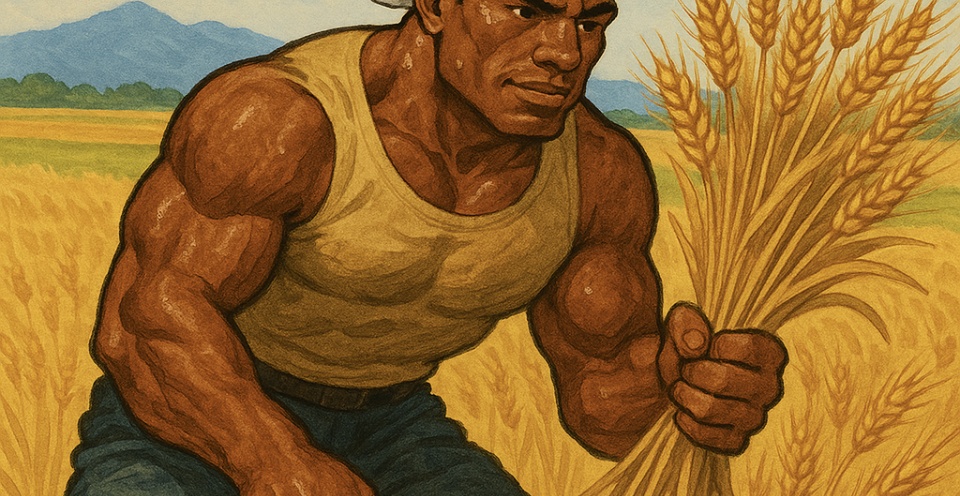
大麦(品種:ファイバースノウ)
上伊那地域の大麦の播種は、10月下旬から11月上旬にかけて行われています。
- 令和6年度は出芽や初期生育は順調で、11月上旬と12月中旬の高温により生育はやや前進しました。
- 1月から2月にかけても高温傾向が続き、特に2月中旬には気温が高く幼穂形成期が平年より早まりました。
- 出穂期は4月24日で、平年より2日早く、前年より5日遅い時期となりました。
- 3月上旬には気温が低下し生育が一時停滞、越冬後は生育量が並~やや過剰気味となり、一部で肥切れによる葉の黄化が見られました。
- 3月下旬から4月上旬は降雨が多く、一部ほ場で湿害が発生しました。収穫期には平年より収量が少なく、平均単収は314kg/10aで前年対比91%、品質は硝子率が許容値を超え、Cランク評価となりました。
小麦(品種:東山53号・ハナチカラ)
上伊那地域の播種は、大麦と同時期の10月下旬から11月上旬にかけて行われています。
- 令和6年度は冬季は高温傾向が続き、2月中旬の高温により幼穂形成期が平年より早まりました。
- 出穂期は4月29日で、平年より4日早く、前年より1日遅い時期となりました。
5月中下旬の降雨により赤かび病の病勢が進展し、6月に一部ほ場で発生が確認されましたが、防除効果によりかび毒DONは基準値以下に抑えられました。 - 6月下旬の多雨では後半収穫分に穂発芽が見られ、品質低下につながりBランク評価となりました。
- 収量は多く、平均単収は362kg/10aで前年対比130%となりました。
今後
冷涼地であるため、現在は2週間ほど遅れての推移となっていますが、今後は地球温暖化により、それぞれの開始時期について年々早まっていくのではないかと考えられます。
沖縄では2月から田植えが始まり、2期作にも取り組んでいるとのことで、その場合8月にまた田植えを行うとのことです。

