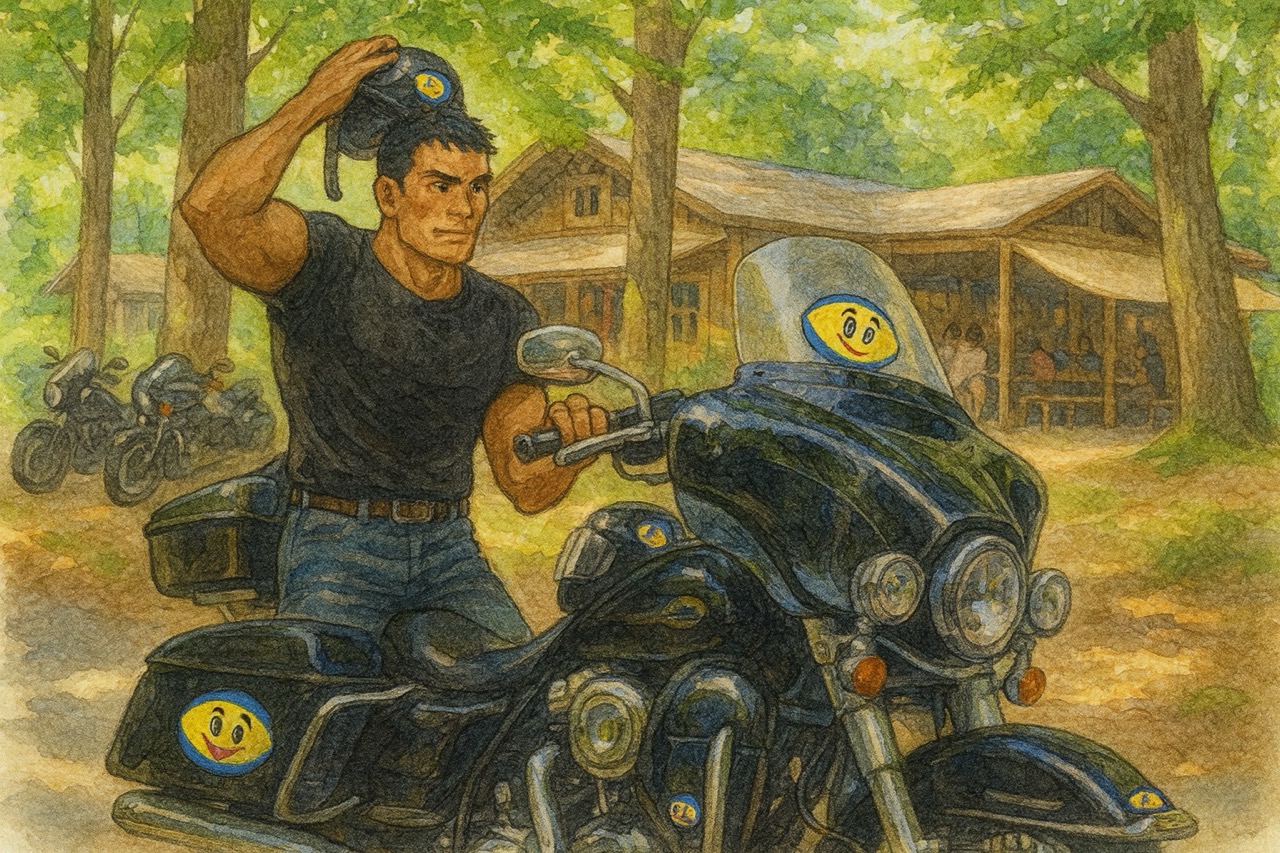南箕輪村議会2025年9月定例会の一般質問で西森一博議員への答弁内容です。
Q1 バイク利用者が増えてきているが、バイク用駐車スペースを設置する考えはあるか
近年、大芝高原への来訪者は増加傾向にあります。
とりわけSNSでステーキランチが話題となり、道の駅でもあることから、バイクでお越しの方が目に見えて増えております。
また、サイドカーも近年はよく見かけるようになりました。
ステーキランチの売上も大きく伸びており、直近の実績でも増加が続いております。
バイク用駐車スペースの設置についてのご質問をいただいております。
法令上、自動二輪は自動車用の駐車場を利用することが可能であり、施設管理者の運用で整理できる事項です。
このため、現時点では四輪用区画をバイクと共同でご利用いただく方針で、専用区画の新設は予定しておりません。
ただし、ステーキランチを提供している周辺は駐車場が不足しております。安全確保は重要です。
混雑や転倒リスクを抑えるため、バイク利用を分かりやすく示す案内、誘導、路面に二輪推奨エリアを明示、といった対策を進めてまいります。
あわせて、事故・苦情の状況を注視し、必要があれば専用区画の設置も含め、運用の見直しを検討いたします。
Q2 「みんなの森」側の駐車場が少ないが、駐車場を拡張する考えはあるか
みんなの森の北側駐車場は、障がい者用3台を含め計46台分を確保しており、二輪車用のスペースもございます。
利用の偏りがあり、平日・休日を問わず午前9時前に満車となる日があることを確認しております。
加えて、令和5年度の村民アンケートでも「みんなの森に近い駐車場を増やしてほしい」とのご意見を頂戴しているところです。
次に、拡張についての考え方でございます。
みんなの森は保安林に指定されており、厳格な制限があり、新たな駐車場を造成することは極めて難しい状況にあります。
そのため、拡張となりますと既存駐車場周辺の樹木を伐採することになります。
担当課からは東に拡張してはとの提案があったことは承知しておりますが、樹木の伐採を伴うことから、慎重に判断したいと考えております。
また、大芝高原森林づくり実施計画(計画期間:令和6年度〜令和12年度)におきまして、森林整備の方針と区画等を定めておりますが、現時点で駐車場のための伐採や造成を前提とした位置づけはございません。
一方、大芝高原には、道の駅や大芝の湯、マレットゴルフ場など既存の駐車場が多数ございます。
そこから徒歩でみんなの森に向かっていただける導線が確保されていること、また満車となるのは時間帯・日にちが限られることを踏まえますと、伐採を伴う拡張まで現時点では行う必要性はないと考えております。
満車時の迂回案内を含む、案内看板・誘導表示の強化については検討事項であるかと存じますが、どちらかというと繰り返し利用される方が多いと認識しておりますので、実施した際の効果は不透明であります。
とはいえ、混雑時間帯の把握など、利用実態の詳細の把握を丁寧に進める必要があると感じます。
Q3 道路交通法が改正して令和8年9月から標識の無い生活道路の法定速度が30km/hとなる。村内で交通量が多く、標識の無い生活道路の実態を把握しているか。
改正道路交通法施行令により、いわゆる生活道路では、標識等で最高速度の指定がない場合の法定速度が、現行の時速60キロから時速30キロへ引き下げられます。
歩行者・自転車の安全確保と、生活圏内の事故抑止を目的とするものであります。
なお、次に掲げる道路は従前どおり法定速度60キロが維持され、今回の引き下げの対象外であります。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
加えて、道路標識等により最高速度が指定されている区間においては、その指定速度が優先されます。
したがいまして、指定が40キロであれば、生活道路に該当しても法定30キロではなく40キロが上限となります。
対象となる「生活道路」については、法令上の表現は“主に地域住民の日常生活に利用されるような道路”であり、一般には中央線や中央帯がなく幅員が5.5m未満の狭い道路が目安とされています。
さて、村内で交通量が多く、標識の無い生活道路の実態を把握しているか、というご質問にお答えいたします。
本村の状況については、道路台帳によれば、村道の総延長は約284km、そのうち車道幅員5.5m未満の村道が約249kmで、全体の87.7%を占めております。
したがって、標示等の有無を精査したうえになりますが、多くの区間が改正後の法定30km/hの適用対象となる可能性が高いと認識しております。
全国的にも、報道や解説資料では生活道路が一般道路の約7割を占めるとの整理が示されており、本村の実情もおおむねこれに合致すると考えます。
一方、速度制限の設定・標識設置を所管する県公安委員会(警察本部)に確認したところ、路線単位で標識や制限速度を一覧できる地図データは現時点で整備されていないとの回答を得ております。
そのため、村で独自に確認を進める必要があり、例えば、中央線がある5つの道路、具体的には
- 久保区の集落から西へ向かう中込線から伊那西部広域農道までの村道1236号線および村道9号線
- 塩ノ井区の集落から西へ向かう春日街道までの村道4号線
- 田畑区の集落から西へ向かう春日街道までの村道109号線
- 神子柴区の集落から西へ向かう春日街道までの村道7号線
- 南原区の集落を通る村道8号線等
については、今後も法定速度が60km/hのままであると捉えています。
また、疑問が出るのがゾーン30の取り扱いであります。
生活道路においては、これまで「ゾーン30/ゾーン30プラス」の取り組みがおこなわれてきました。
ゾーン30については、警察庁は今回の生活道路の法定速度の引き下げ後も、「ドライバーへの周知効果がある」として制度を継続する方針を出しています。
また、国土交通省はゾーン30プラスについても引き続き、30キロ制限の道路を対象に拡大を目指す方針であります。
ドライバーの意識として、これまでは、速度標識を見れば「減速」を意識しましたが、今後は生活道路の原則30km/h化により、むしろ標識のある区間=30km/hを超えて走行できる区間それ以外は原則30km/hという受け止め方へ意識が切り替わっていくのではないかと考えております。
Q4 住民への理解が重要だと考えるが周知方法は。
生活道路に係る法定速度の引き下げは、生活道路での車両速度を抑制し、歩行者の安全確保と事故防止を図ることを目的として、昨年7月に道路交通法施行令が改正・公布されたものであります。
背景には、一般に時速30km/hを超えると歩行者の致死リスクが急増するという知見があり、速度規制を主管する警察庁・都道府県警がウェブサイトやチラシ等で周知を進め、報道でも取り上げられてきました。
今後、施行時期が近づくにつれ広報は一層強化される見込みですが、地域への浸透には地元自治体との連携が不可欠であります。
村といたしましても、警察・村交通安全協会と連携し、制度の意義や目的を丁寧に説明したうえで、わかりやすい周知・啓発に取り組んでまいります。
周知手段につきましては、高齢者層にはテレビ・ラジオ・新聞・地域の広報紙が有効とされておりますことから、広報紙や回覧板等で複数回にわたり情報発信し、確実な定着を図ってまいります。
標識の取扱いについて申し上げます。
村として生活道路一帯に新たな「30km/h案内板」を一律に設置する考えは持っておりません。その代わりに、「標識のない生活道路は法定30km/h」という考え方を浸透し、速度超過の抑制につなげてまいります。
あわせて、個別の危険箇所については、案内板の設置やハンプ等のハード対策も含め、従来どおり個別に検討してまいります。
なお、中央線等が設けられ、今回の改正の対象外となる道路につきましては、引き続き法定速度は60km/hでありますが、安全上の観点から速度引き下げが必要な区間については、公安委員会に対し最高速度の指定や標識設置を要望してまいります。
ご質問の回答には外れる部分がございますが、361号は50キロに規制されていますので、村道については基本的には50キロ規制を設けることができないかなどは合わせて要望していく必要があると感じております。
Q5 民生児童委員のなり手不足の原因とその課題とはなにか。
民生委員は民生委員法で市町村に設置が定められ、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、住民の立場から生活や福祉全般に関する相談に応じ、行政や地域の支え合いにつなぐ役割を担っています。
また、すべての民生委員は児童福祉法により「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。
本年は3年に1回の一斉改選の年に当たり、村でも定数30名の委員について、県へ推薦を行ったところです。
推薦に当たっては、従前どおり、各区で候補者の選定を行っていただきましたが、非常に大変であったという声を多数いただいています。
民生委員のなり手不足については本村に限らず全国的な課題となっており、全国では、前回令和4年の一斉改選では1万5千人余の不足が生じ、充足率は93.7%となりました。
これは令和元年の一斉改選と比べ、それぞれ3,700人、1.5%のマイナスとなっています。
民生委員のなり手としては、これまで、定年退職した人など仕事や育児が一段落した人が担うことが多かったと考えられますが、定年延長や再雇用等で地域活動を担える年代が上昇していること、区への加入者減少等地域住民同士の結びつきが薄れたこと等により、民生委員候補者として区の役員が声をかけることができる方が少なくなっている状況だと考えています。
また、民生委員の任期は3年と長期間であること、その職務内容は大変であるというイメージが先行していることも、なり手確保の足かせになっていると感じているところです。
一方で、身寄りのない高齢者や社会的に孤立する人も増える中で、民生委員への期待や役割は増していると認識しているところです。
Q6 村として支援や負担軽減を行っているのか。また各地区の定数見直しの考えは。
村としての支援・負担軽減について、本村では、民生委員の皆さまが安心して活動できるよう、以下の支援を行っております。
待遇面の支援として、民生委員法上は基本無報酬ですが、県から活動費 年額60,200円/人、村から福祉事務調査委員として年額124,800円/人を支給しております。併せて、各種研修への参加費助成を実施しております。
次に活動の整理と心理的負担の軽減として、独居高齢者等への声かけ・見守りについて、地域のつながりが希薄化する中で重要な役割ですが、「家庭の内情に深く踏み込む」のではなく、住民目線で“気になる点があれば福祉課につなぐ”ことを基本としてお願いし、過度な心理的負担が生じない運用に努めております。
事務負担の縮減として、かつてお願いしていたタクシー利用料金助成事業の申請世帯調査は、現在は依頼しておりません。
今後も、役割と事務の適正化を図り、過重な負担の発生を避ける運用を継続いたします。
次に、各地区の定数見直しについてであります。
民生委員の定数は都道府県条例で定められるもので、長野県では一斉改選のたびに市町村の意向を確認し見直しが行われます。
本村は、町村で概ね70~200世帯に1名という基準、各地区の状況、活動実態等を総合的に勘案し、村民生児童委員協議会で各委員のご意見も伺ったうえで、本年の一斉改選では定数を変更しないことといたしました。
引き続き、一斉改選の機会に、人口動態や地域ニーズ、活動量などを踏まえて見直しの要否を検討してまいります。
Q7 村としても積極的に候補者の掘り起こしをする必要があるのでは。
ご指摘のとおり、村としても主体的に候補者の掘り起こしを支援する必要があると認識しております。
本年の一斉改選では、従前どおり各区主体で候補者選定をお願いしつつ、一部の区では担当職員が説明役として区役員と同行し、地域を回ってまいりました。
今後も、地域の実情に最も通じる各区による選定を基本としつつ、村の支援の質と量を拡充してまいります。
また、選定を行っていただく期間や、民生委員活動の住民への周知等広報活動については改善の余地があると考えています。
次回令和10年度の一斉改選に向け、各区での候補者選定がスムーズに行えるよう、必要な取り組みを行いたいと考えています。
なお、候補者確保に難渋する地区については、今回と同様に職員が同行・説明に入るなど個別支援を継続いたします。
各区の自主性を尊重しつつ、村が前面で見える支援を行うことで、担い手の不安を和らげ、着実な選任につなげてまいります。