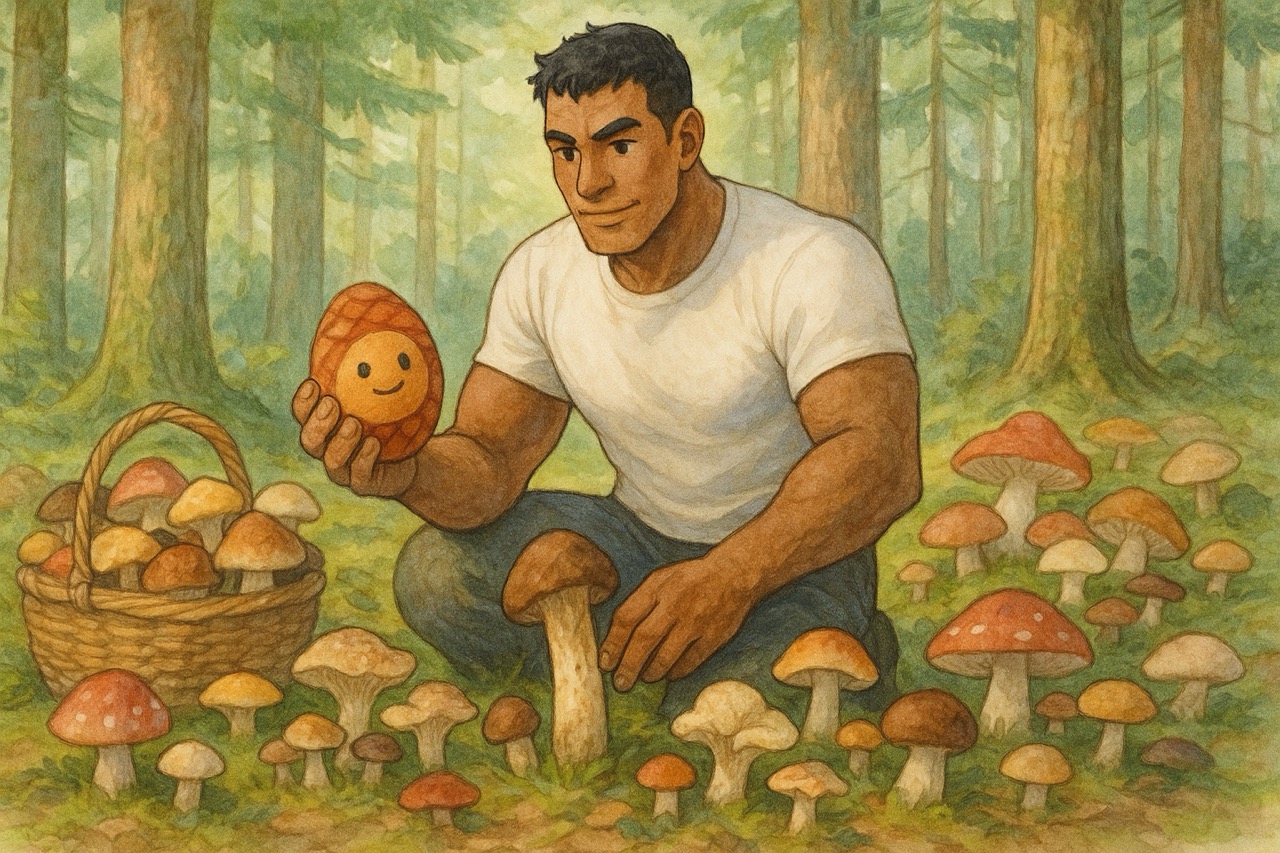大芝高原はアカマツを中心とした平地林となっており、マツタケは獲れる?獲れない??とよく聞かれます。
そこで今回は、大芝高原のキノコ事情について調べてみました。
大芝高原林のキノコ事情については、少し昔の話にはなりますが、1999年に信州大学農学部の大芝公園林研究会が発行した「大芝高原林調査報告書」に詳細の記載がありましたので、それを参考にさせていただきました。
なお、調査研究者の澤畠拓夫さんは、現在は近畿大学で活躍されている博士です。
「大芝高原林調査報告書」は村図書館や村役場のホールで読むことができますよ。
調査の概要
今回取り上げる、1999年発表のキノコ調査は、大芝高原のアスレチックがある区画で行われました。
この区画は、ほとんどがアカマツ純林と言っていい環境であり、宿主となる樹種が貧弱な状況であるとのことです。
そのため、きのこの発生種類は75種と、専門的には少ない結果となりました。
一方、きのこの発生量は多いとのことです。
大芝高原のキノコの特徴
大芝高原のキノコ事情の結論としては、アカマツと共生する菌根菌が豊富にみられるとのことでした。
アカマツ林を代表する菌根菌は、アミタケやハツタケ、ヌメリイグチなどであり、これらが大芝高原では比較的豊富にみられ、キノコ狩りに来る人々を楽しませているとのことです。
キノコ(食用)
マツオウジ:臭いがきつくあまりおいしくない

オオキツネタケ:晩秋にはシモタケとして採取するひとも

クロハツ:食べると柄がしゃきしゃき
オウギタケ、シロハツ、カワリハツ、ムラサキナギナタタケ、ガンタケ、カイメンタケなどが発生しています。

優秀な食用菌
アミタケ、ハツタケ、ヌメリイグチ、クリタケなどが発生しています。
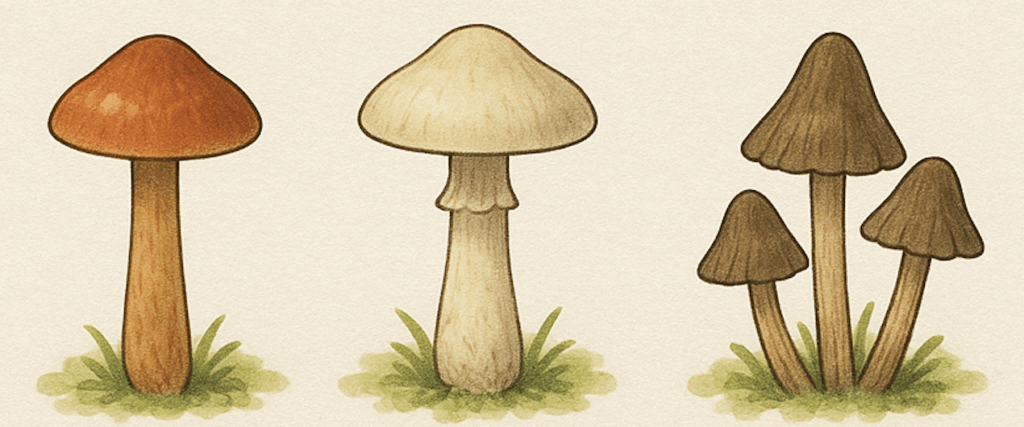
毒キノコ
フクロツルタケ:死亡事例あり
カキシメジ:何回かゆでこぼせば食べれる?
ニガグリタケ:クリタケに似ているレモンの傘
テングタケ、オオキヌハダトマヤタケ、アセタケの仲間が発生していますので、ご注意ください。
ところでマツタケは?
マツタケは大芝高原に発生しているのでしょうか。
残念ながら、報告書によれば、マツタケの発生は確認できなかったとのこと。
大芝高原のような平地林では、マツタケが発生するような環境を維持管理するのは困難であることが理由として挙げられています。